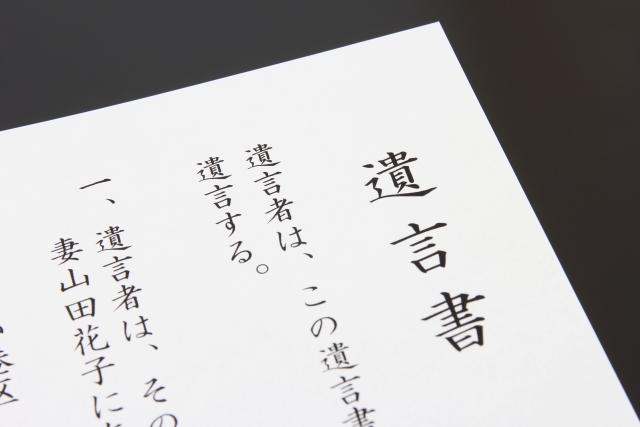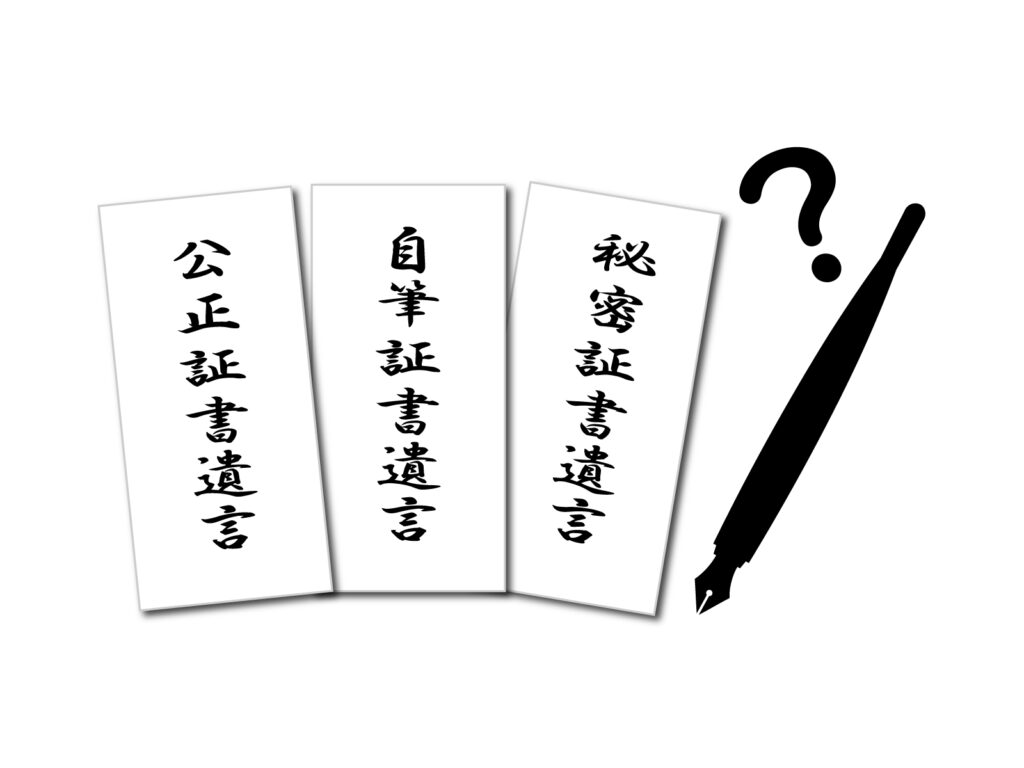
Q遺言の形式にはどのようなものがありますか。
A遺言には、普通形式による遺言と特別形式による遺言があります。普通形式の種類として①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言があります。特別形式の遺言は、例外的な場合に認められ、危急時遺言と隔絶地遺言があります。
この記事では、①自筆証書遺言、②公正諸所遺言、③秘密証書遺言の違いとメリット、デメリットをお伝えします。
| 方式 | メリット | デメリット | |
| 自筆証書遺言 | 遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、押印する(民968条)。 | 遺言者本人のみで作成することができる。遺言書は原則自ら保管する。※1 | 遺族が保管してあることを知らないと、遺言書を見つけてもらえない。 方式が違うと効力が問題となることがある。 家庭裁判所で検認が必要になる。 |
| 公正証書遺言 | 証人2人以上が立ち合い、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が筆記して遺言者・証人に読み聞かせ又は閲覧させ、遺言者・証人が承認して署名押印し、公証人が署名押印する。(民969条) | 遺言の内容が明確であり、紛争の生ずるおそれが少ない。 原本を公証人が保管するため、紛失・偽造のおそれがない。 家庭裁判所の検認の必要がない。 | 証人や費用が必要となる。 公証人・証人には、遺言を秘密にできない。 |
| 秘密証書遺言 | 遺言者が遺言書を作成して署名押印の上、封印し、封書を公証人・証人2人以上の前に提出し、自己の遺言書の旨及び氏名住所を述べ、公証人が日付及び遺言者の口述を封書に記載し、遺言者・証人と共に署名押印する。(民970条) | 遺言の内容を秘密にできる。 遺言書の偽造、変造のおそれがない。 | 方式が違うと効力が問題となることがある。 家庭裁判所の検認が必要となる。 |
※1 自筆の遺言書は、遺言者の申請により、法務局で保管することができ、当該遺言書については、家庭裁判所の検認を要しない。